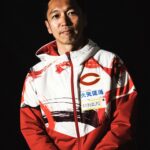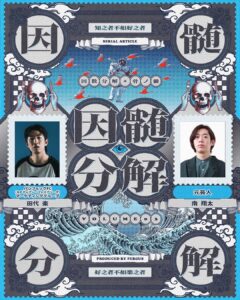箱根の鍵を握るのは“中間層”のブレイク
この取材を行ったのは6月28日。ちょうど男鹿駅伝が開催された日だった。男鹿駅伝は秋からの駅伝シーズンへの“前哨戦”として注目されており、今年も青山学院大学を筆頭に、東京国際大学や東洋大学など、今年の箱根駅伝でトップ10にランクインした有力校も数多く参加した。
連覇を狙った中央大学は、青学に次いで2位でフィニッシュ。藤原正和監督は、つい先ほど終わったばかりの大会について、次のように総括した。
「2位は2位ですが、圧倒的にやられたなと」
人選には、箱根に向けた明確な意図があった。
「チームのトップ層ではなく、箱根の16人に入れるかどうかの中間層の選手たちを今年は選びました。このグループがいかに力をつけるか。それがチームとしていま一番の課題で、彼らが青山学院さんと戦えるようになっていかないと、箱根での優勝は難しいと感じています」
その狙いは、この大会でどのくらい成就したのだろうか。出場したそれぞれの選手に対する監督の評価を聞いてみた。
「1区の七枝直には及第点をあげられますが、70点くらいです。伊藤春輝(2区)は登りでよく粘ってくれたので、80点というところでしょうか。3区の並川颯太は、体調を崩した後の走りと考えればまずまずですが、はっきり評価すると物足りない部分があり、50点という感じです。
4区の相地一夢に関しては、ブレイクを期待してここに抜擢していますが、今日は良くなかった。5区の鈴木耕太郎は、東京国際大の菅野選手と同タイムということで、自分の力を発揮できたと思います。80点はあげられるのかなと。
6区の三宅悠斗にエース区間を任せたのは、“チームの次の主軸に”という思いがあり、いろんな経験を積んでほしいからです。全日本大学駅伝選考会から日本学生対校を経て、今回もしっかりとやり切ってくれたので、今後どこかで跳ねてくるのではないかと。
相地と同様に良くなかったのは、アンカーの伊東夢翔。彼の場合はいい時と悪い時がはっきりしすぎていて、このままだと厳しいと言わざるを得ないです」

『結果が出ないと和はできない』
結果を残せなかった選手には、単刀直入に厳しい評価を下す藤原監督。中間層の選手たちへの期待がそれだけ大きいということだろう。ただ、チーム全体の雰囲気は決して悪くないと語る。
「去年のチームは和を大事にするチームでしたが、逆に言えば、“和から入って結果を出そうとしすぎていた”という反省もあります。
だからこそ、『結果が出ないと“和”というのはできないよ』と今年は伝えていて、“結果にこだわりながら、全員で切磋琢磨して強くなろう”というチームになってきているので、全体の雰囲気としてはいいと感じています」
その上で、今回のような負けをどう活かすかが重要だと藤原監督は続ける。
「今日みたいな負け方をした時に、走った選手たちが何を感じて、それをどのように練習と生活に落とし込んでいくか。そこにチームの変革がかかっています。青山学院さんは何人か主力選手が走ったという側面はありますが、それを差し引いても、『もっとできたんじゃないか』と彼らが感じられるかどうか。それがすごく大事です。
もちろん、選手たちは『このままで終われない』と思いながら帰ってくると思いますが、3日で忘れるのではなく、ずっとそう思い続けて、ここからの半年間を頑張れるかどうか。そこはチーム全体でしっかりと共有していきたいと思っています」

自信と言語化の相関性
前回のインタビューでは、チームに“勝ち癖”を植え付けたいと話していた。その文脈において、今回のように期待されたような結果を残せなかった選手、あるいは明確な勝利を掴み取った経験のない選手には、どのようにすれば自信を身につけさせられるのだろうか。
「結局はどの分野でも同じだと思いますが、自分の中でスモールステップを作り、それをきっちりとクリアしていくこと。それでしか自信は成り立たないと思います。
そういう意味では、毎週のポイント練習を確実にクリアしていく、あるいは余裕を持ってクリアする。さらに言えば、その余裕をどれだけ増やしていけるか。それが一つのステップになりやすい。一つずつちゃんとクリアさせていくことで、自信を植え付けさせたい。“チーム内のポイント練習であの選手に勝ったことがなかったけど勝った”という経験でも十分なので、自分が強くなっていることを実感してもらいながら、自信にしていってもらいたいなと常に考えています」
掴み取った勝利に対する捉え方は、人それぞれだ。ポイント練習の勝ちで自信を積み重ね、着実に成長していく選手もいれば、結果を残しながらもなかなか自信を身につけられない選手もいるだろう。
選手の個性を簡単に一括りにすることはできないが、総じて、長距離選手はどのようなメンタルで練習と自分自身に向き合い、自信を身に付けていくべきなのか、藤原監督の考えを聞いてみた。
「長距離走はサッカーやバスケなどと違い、周りとコミュニケーションを取りながら試合を進める必要がない種目です。結局は“苦しい時にいかに自分に打ち勝つか”がメインの競技なので、基本的に長距離選手は、自分自身に集中する力がすごく研ぎ澄まされていきます。
その一方で、他の競技に比べ、社交性が低くなる傾向がある。その社交性をいかに持ち、私生活を含めた自分の考えや悩み、ぶつかっている壁について、アウトプットしていけるか。言語化させる能力を磨いていけるかが、自信を持つ上でも重要です。
たとえば『自信がある』と言える選手がいたとしても、それが根拠のない自信では、指導者としても困るわけです。『〇〇が良かったから、すごく自信を持って取り組めています』と、しっかりと言葉として言えるようになることが非常に大切だと思います。
プラスアルファで言えば、スピード練習の際に『お尻がギュッと入って、バーっといけました』という擬音での説明よりも、『この筋肉に〇〇くらいの負荷がかかっているから、これくらい走れました』と数値で言えるようになるともっと良い。そういう指導もできる限り行っています」
Track Night Viennaがもたらしたもの
6月にウィーンで開催されたTrack Night Viennaには吉居駿恭、溜池一太、濵口大和らを送り込んだ。藤原監督が就任してから積極的に推し進めている海外遠征の一環だ。今大会への出場も、目的は明確だった。
「5000mでの世界選手権を狙うにあたって、ポイントランキングを稼ぐためです。標準記録は非常に厳しいハードルなので、カテゴリーの高いレースで少しでもポイントを稼がないと、世界は狙えない。
その中で溜池は積極的に13分15秒のペースについていき、自己ベストを出してくれましたし、非常にいいレースだったのではないかと。濱口はその力を期待されて入ってきたわけですが、高校と大学の違いに足踏みしている時期があったので、少し自信を取り戻させたいと思って送り出しました」
この遠征から帰ってきた選手たちの行動に、一つの成長を見出したと藤原監督は語る。
「柴田大地を含め、遠征に行った4人の選手が『この時期に行かせてもらい、ありがとうございました』と言ってきたんです。チームとして箱根駅伝での勝ちを狙っている中で、海外のトラックレースに行くのは当たり前ではない、ということは彼らも当然分かっていて。
特に駿恭には、キャプテンとして色々なストレスがあると思います。その中で、『少しチームを離れてチャレンジさせてもらえたことが非常にありがたかった』と。そういうことを自然と言えるようになってきている彼らの人間性に成長を感じました」

この夏をどう過ごすか
長距離走にとって厳しい夏を、どう乗り切るか。それが秋以降の勝負を決める。
「選手にとっては、テストと課題で睡眠も削られる7月が1番厳しい。なので、無理してポイント練習はやらせずに、ジョグでもいいので、練習の“継続”させていくことが大切です。
まずは学生の本文である学業をメインに進めてもらい、体はリフレッシュさせて上期の疲れを取るイメージで送らせるように意識しています。その上で、夏季記録挑戦競技会や日本選手権が上期の締めとしては重要なレースになるので、6月にやってきたことをしっかりと発揮してもらいたいなと思っています」
今年は梅雨入り頃から夏本番のような暑さに見舞われたが、部内だけではなく外部とも連携しながら、夏対策を進めているという。
「夏はただでさえ体温が上がりやすいのに、発汗量が多く、体の深部温度が冷えにくい。そこが1番の戦いになってくるので、いかに練習中に深部温度上げないように走らせるか。あとは練習で上がった深部温度を、いかに下げて夜の睡眠に入れるかを繊細に意識してやらないと、その日の疲れがその日のうちに取れません。そのケアはやはり大変です。
そういった面を含めて、2週間に1回、大阪体育大の石川昌紀先生に来ていただき、最適な夏対策を徹底しています。夏の間も、できるだけいい常態で日々のコニショニングを保てるかにフォーカスして進めています」
季節の移ろいは、箱根までに残された時間がジリジリと短くなってきていることを意味している。現在のチームの完成度について聞いてみた。
「上半期の強化は、計画していた8割はできました。ただ、残りの2割——“中間層の底上げ”は後手を踏んでいるイメージです。この夏がやはり一番大きな勝負。7月、8月、9月、この3ヶ月の強化期間を、とにかく故障なく、離脱者なく過ごしていき、いいリズムで秋のシーズンを迎えたいというのが、今の気持ちです」
PROFILE
藤原正和(Masakazu Fujiwara)

著者
佐藤麻水(Asami Sato)