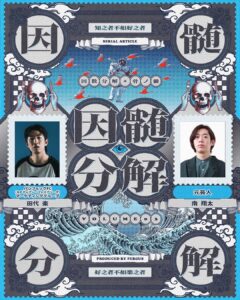第101回箱根駅伝(2025)、総合5位。まさかの予選からの出場となった中央大学陸上競技部長距離ブロック(以下、中央大学駅伝部)は、しっかりと一年で軌道修正し、来年のシード権を掴み取った。
箱根駅伝の長い歴史において、中大は歴代最多の優勝14回という記録を誇る。しかしながら、2013年から2021年までは低迷期と呼べるような状況で、シード権圏外や不出場が続いた。近年は名門復活の兆しを見せており、10年ぶりにシード権を獲得した2022年(6位)に続き、2023年は準優勝を果たした。
そのきっかけを生み出したのは、現監督の藤原正和に他ならない。中大が37年ぶりの往路優勝を成し遂げた77回大会で、往路のゴールテープを切った張本人である藤原は、卒業後にホンダの実業団ランナーとして活躍。ベルリンマラソンや世界陸上などの出場を経て、2016年に監督として母校にカムバックした。
彼はどのようにして中大駅伝部を復活させたのか。学生たちに何を伝え、何を授けたのか。先の箱根駅伝や今年の展望、指導法について話を聞いた。
失意からの再出発となった2024年
吉居大和に中野翔太、湯浅仁などの強力なランナーを擁し、周囲からも優勝候補の一角と目されていた第100回箱根駅伝(2024)。しかし、集団発熱という異常事態により、結果は13位。大きな失望から2024年シーズンのスタートを切ったわけだが、この1年間を評価するとしたら100点満点中の何点になるのだろうか。
「シーズンを通しては75点から80点の間というところです。箱根駅伝に関して言えば95点をあげられるような出来だったと思います。シーズンを通して苦しんだところが多々あったのですが、箱根ではうまくいった点が非常に多かったのかな、といまは捉えています」
前回大会の苦い経験はチームの足元を見直すきっかけになり、それが今年の箱根に繋がったと語る。
「100回大会に関しては、1年間を通じて優勝を意識して、全員でそこに向かって進んでいきました。ただ、本当の意味で優勝を狙えるチームではなかったからこそ、足をすくわれるようなところがあり、あのアクシデントが起きたのではないのかなと思っています。
それを踏まえて、基礎と基本を大切に、地道なところをもう一度きっちりとやっていこうと。もちろんそれまでもやっていたのですが、より精度を上げました。朝に体温や血圧、脈を計測し、血圧差の変動をグラフにして、その開きが大きい時は体調を崩す前のサインということで早めに対策を取ったり、そういう細々としたところにこだわりを持ったのがこの1年間でした。
やはり昨年のショックというのは、我々にとって非常に大きかったです。2度と起こしてはいけない、そして2023年のチームが強かったということを証明したいという想いが2024年のチームにはあったので、なんとか最後にそれを達成させられたのではないかなと感じています」
箱根駅伝が終わり、気づけばもう桜が咲く頃だ。新キャプテンに任命されたのは、今年の1区で区間賞を獲得した吉居駿恭。吉居が引っ張っていく新しいチームは、どのようなチームスタイルなのだろうか。
「昨年は佐野拓実がキャプテンで、力的には中間層だった子がいろんなところに目を配る、というチーム作りでした。今年はエースである吉居駿恭が新キャプテンになり、練習でも生活でもその背中を見せて言葉でまとめていくという、去年とはまた違う形で、非常にまとまりはいいのかなと。
いまの3、4年生たちは、優勝を目指して1年間活動し、それを実際に達成する難しさをすでに経験しているので、より細かいところに目を配っていると思います。あとは下級生の生徒たちがいかにベクトルを優勝に向けられるかが、いまの大きなテーマです。上級生はそこへのテコ入れも含めて、すごく頑張ってくれているなと感じています」

「走っている選手と生活している選手は同じ」
キャプテン任命は監督の意向ではなく、4年生たちのミーティングによって決まるという。その人選の意図を含め、選手と監督コーチ陣の間で細かくディスカッションを重ね、最終的な人選と目標を定める、という流れだ。選手たちの意思をより尊重するチームマネージメントと言えるだろう。
おそらく、藤原監督自身の時代と比較すれば、選手のメンタリティは大きく変わったはず。藤原監督はその変化を踏まえた上で指導に当たっていると話す。
「自分たちのことを昭和の生き残りと呼んでいるのですが(笑)、やはり昭和や平成の頃と今は全然違います。『こういう風に伝えたら、彼らはどう捉えるだろうか』という部分まできめ細かく考えて、タイミングやアプローチの仕方をしっかりと測った上で接するように意識していますね。
競技面で言えば、チームのレベルが上がってきたことでティーチングの段階が終わり、コーチングに移行して、そこからさらに進んで、上位層の子達には1選手と1コーチとして対等に意見を交わしあうフェーズに移ってきているのかな、と感じています。
生徒たちの意見を尊重しつつ、とはいえやはりまだ学生なので、抑えないといけないポイントはしっかり抑えつつ、この先どうやって伸ばしていくかっていうところを、個々と集団にアプローチしているような形です」
選手たちの自主性を育みながらランナーとして成長させる上で、普段どのようなことを意識しているのだろうか。
「とにかく現場に出ることです。朝練習から学生たちと顔を合わせて、表情を見て言葉を交わしていく中で、一人一人の変化を少しずつ読み取っていく。ちょっとした変化に気づいていくには、結局はコミュニケーションの質を高めていく必要がある。この一点は昭和の時代から変わらず、どの時代でも大事なのではないかと思っています」
藤原監督が中大駅伝部に戻ってきて、今年で10回目の春を迎える。就任から数年は苦しい状況が続いたが、見事な手腕で中大をトップ層へと再び押し上げた。もし監督1年目の自分自身にアドバイスを送れるとしたら、どのような声を投げかけるだろうか。
「『すごく苦労するぞ』ということですね(笑)。ただ、苦労はしましたが、『今の自分だったらあの時どう行動しただろう』と考えてみても、『今でも同じようにしただろうな』ということが多いです。
徹頭徹尾と言いますか、『ここが文化を根付かせないといけないポイントだ。これを根付かせていけば、常勝チームになっていくための礎ができる』という出来事が、最初の5年に数多くありました。当時の選手たちは本当にしんどい思いをしたと思いますが、それがあったから今のチームが出来上がっている、ということは間違いなく言えるので、『しんどい5年だけど頑張れ』としか自分に言ってやれないですね」

藤原監督が中大駅伝部に根付かせた文化。それは言葉にすれば単純なものかもしれないが、一朝一夕で完成するものではない。
「陸上は、頼れる道具はシューズしかなく、それ以外はすべて自分。結局、自分の体とマインドをいかにコントロールして、スタートからゴールまで最速で駆け抜けるか、という競技です。
自分の体とメンタルのコンディションを最上に持っていくために1年間を費やし、箱根駅伝にアプローチしていくためには、『走っている選手と生活している選手は同じだよ』ということを気づかせることが必要です。そして、それを行動に落とし込んでもらう、さらにはそれを文化として根付かせるまでに、すごく時間がかかりました」
スピードで箱根を制する
藤原監督の頭の中には、“スピード駅伝で箱根を制す”というプランがあるという。それを達成する上で、どのような練習で落とし込んでいくのだろうか。
「基本的には寒いシーズンか涼しいシーズンでなければ記録はなかなか出にくいので、これから迎える春夏シーズンは、各選手それぞれが様々な種目にアプローチしていってもらいながら、力をつけていってほしいと思っています。その力を持った上で、夏合宿で駅伝仕様にだんだん体を変えていき、出雲と全日、あるいは各種ハーフマラソンを戦いつつ、だんだん箱根仕様に体を変えていくイメージです。
あとはマーチ対抗戦が我々にはあります。そこで27分台(10,000m)を10人以上は絶対に出そう、という目論みがあります。それが達成できれば、『スピードをもって箱根を制する』というプランの実現性が見えてくる。そう思い描いてこの2ヶ月間を進めてきました」
この取材は3月13日に行われた。先週、新入生が入寮し、少しずつ緊張が解れてきた頃だという。新1年生で箱根駅伝のメンバーに食い込んできそうな選手はいるのだろうか。
「持ちタイム13分台(5,000m)というのが高校生トップレベルの証だと思いますが、濵口大和(佐久長聖)、三宅悠斗(洛南)、辻誉(福岡第一)という3人はそのタイムを持って入部してくれます。この3人はおそらく1年目から絡んでくるだろうなと。
特に濵口大和に関しては、13分31秒(5,000m)で走るので、ハーフ対応がきっちり出来てくれば、1年目から往路でも十分に使える可能性があります。もちろん無理をさせない、というのが大前提ではあります。『このチームで1年目から箱根で優勝したい』と彼らも言っていますので、できるだけのことをして、彼らが戦えるように間に合わせたい、準備させたいと考えています」

“NEXT青山”=次は絶対に中大の時代が来る
近年の中大駅伝部は、アメリカ遠征や海外での合宿を積極的に行っている。その部分に魅了されて入部を希望する選手も多くいるだろう。聞けば、これらの取り組みは藤原監督自身の経験や反省から生まれたものだという。
「予算の限界は当然あるのですが、できるだけ外に行かせたいと思っています。
自分自身、アテネ五輪に始まり北京、ロンドン、リオを目指しましたが、結局オリンピックには行けず、世界選手権止まりでした。『なぜオリンピックに行けなかったんだろう?』と考えた時に、『自分の行動に少しでも多く変化を起こして、それを継続させていれば、もしかしたら手が届いたんじゃないか』と思うことがあり、いまの生徒たちには同じような想いをできる限りしてほしくないなと。
外の世界に出て、英語の必要性を若い時から感じたり、海外には人種差別がより日常として存在することを知ったり、なんでもいいので感じ取って、それを自分の行動の変化に繋げてほしい。
あとは、せっかくこの職に就いたので、オリンピックに出る選手を育てたい。1人でも多くその可能性を広げて、チャンスを掴んでくれるようなことがあれば嬉しいので、その機会作りです。
最初は学内でも、『箱根に海外遠征は必要ないでしょう』という声も沢山いただきました。ただ、こうした想いを伝えて、なんとかご理解いただいて、いまは継続して海外に行かせてもらえるようになり、海外を経験した選手たちは大きく成長して帰ってきてくれます。
社会人になった生徒たちがオリンピックに出たり、日本代表になったりしてくれれば、1番成果があったと言える取り組みなので、送り出した子たちの活躍にも期待しています」
中大が箱根駅伝で最後に優勝したのは、1996年の72回大会。30年越しの優勝を狙う中大駅伝部は、今後どのようなアイデンティティを築いていくのだろうか。
「いまは原晋監督や原メソッドが有名で、チームとしても青山学院大学さんが最強のチームだと思いますが、『次は絶対に中大の時代が来る。“NEXT青山”だよ』とチーム内で言い合っています。
プラスアルファ、世界レベルの陸上に追い付くためには、やはりスピードからのアプローチで箱根を制する必要がある。それをしっかりと形にすれば、世間に対して説得力を持って自分たちのやり方を示すことができると思いますし、『じゃあ俺たちでやってやろうよ』と。
いま目指しているのは、10000m27分台10人、戦力として揃えるということ。それをよりブラッシュアップさせて、次は27分45秒、その次は27分30秒で10人揃える。それがいまの私に与えられているミッションなのかなと感じています。それが日本の陸上界のレベルアップに繋がっていけば、なおいいと思います」

最後に、日頃から中央大学駅伝部を応援している方に向けてメッセージをもらった。
「苦しかった100回大会の結果から、学生たちが頑張って立て直し、なんとか5位というところまでは戻ってきました。とはいえ、シードを取るのが我々の仕事ではないということは分かっています。
『次の時代を作るのは我々中央大学だ』と思って、ここ9年我々はやってきましたので、なんとしてもまずはこの10年目で1つ大きな花を咲かせて、自分たちの時代を築いていきたいです。
他の大学さんとも引き続き切磋琢磨して陸上界を盛り上げて、いずれマラソンでメダルを取れるような選手を育成できればなという思いですので、またこの1年、ぜひ応援していただければと思います」
PROFILE
藤原正和(Masakazu Fujiwara)

著者
佐藤 麻水(Asami Sato)