
「海外ではスポーツエグゼクティブが注目されることがありますけど、今後は日本でももっと脚光が当たるきっかけになるといいな」
インタビュー開始前にそう語ってくれたのは、NYに拠点を置くBlue United Corporationの代表·中村武彦氏。MLS初の日本人スタッフとして、FCバルセロナのアメリカツアー、環太平洋の大会『パンパシフィックチャンピオンシップ』創設を手掛けた後、バルサから招聘を受け転職。その後もアレッサンドロ·デル·ピエロの来日ツアー開催や、数多くの日本人選手のアメリカ移籍など、スポーツビジネス界の先駆者として、世界と日本のサッカーを繋げてきた。
町田生まれで、幼少期をアメリカで過ごし、8歳でサッカーと出会った。10歳で日本に帰国した頃、日本語が苦手だった中村氏の順応を助けたのは、当時の『キャプテン翼』ブームだったという。青山学院大学サッカー部でプレーした後、「海外の仕事がしたい」と漠然と考え、NECに入社する。
しかし、NECでの仕事は中村氏にとって刺激的なものではなかった。商材である光海底ケーブルの教科書を渡されても、興味が湧かず仕事中に寝落ち。“しがないサラリーマン”である自分と、世界で活躍する“同学年のスーパースター”を当時よく比較していたという。
「ちょうどその頃、中田英寿選手がペルージャに移籍して大スターになっていて。一方の僕は満員電車に揺られ、仕事も楽しくない。『同い年で、おそらく同時期くらいにサッカーを始めて、おそらくそこまで差がないところから、いつからか雲泥の差が生まれたな』と(笑)」

NECの仕事に対して「この会議がサッカーに関するものだったらもっと楽しいのに。スポーツの仕事ってないのかな?」と感じ始めた頃、研修でワシントンD.C.に出張することに。その研修が中村氏の運命を少しずつ動かしていく。
「子会社立ち上げに関する会議で、僕は単なる新人の研修として座っているだけなんですが、マーケティングの打ち合わせになると、相手はMBAが来て『君が日本側のMBA?』と聞かれて。契約書の話になると弁護士が出てきて、『君も弁護士?』と。会計の話ではCPAが出てきて、『君もCPA?』と聞かれ、『いや、営業部です』と答えると、向こうは怪訝な顔をするんです。その時に悟ったのは、今後の3年間で僕はマーケティング·法律·ファイナンスを1ブロックずつ重ねるけど、彼らはそれぞれの専門分野を3つ重ねられる、ということ。つまり、3年で2ブロック、6年だと4ブロックの差が付くわけです。『これは勝てるわけがない。何かのプロにならなきゃダメだ』と危機感を持ったんです」

危機感だけではなく、新しい目標もアメリカ研修で見つかった。D.C.ユナイテッドの試合をスタジアム観戦した中村氏は、「北米リーグは倒産したけど、自分が育った国でまたプロリーグができたんだ。こういうところで働くにはどうしたらいいんだろう」と感じ始めたそうだ。
帰国した当初は、アメリカで芽生えた目標への取っ掛かりは何もなかったという。そもそも、当時の日本では“スポーツビジネス”というものがまだ確立されていなかったのだ。
そんな状況の中、『スポーツナビ一ゲーション』を立ち上げた広瀬一郎氏と本間浩輔氏との出会いや、『IMG東京支社』設立を報じる新聞記事などを通じ、「スポーツビジネスというものがあり、アメリカではそれをアカデミックに勉強できるらしい」と知り、留学を決意。マサチューセッツ州立大学大学院で、スポーツビジネスのメソッドを学び始めた。
「“サッカー不毛の地”と言われていたアメリカで、メソッドを使ってMLSがどのように成長するのか見てみたいと思ったんです」
そうは言うものの、またしても何も取っ掛かりはない状況。卒業生を介してMLS国際部の知り合いはできたが、そこからどう繋げるか。中村氏が思い付いたのは、「卒論のアドバイザーになってくれませんか?」とお願いすることだった。その依頼が受け入れられ、定期的に会う口実を取り付けた。マサチューセッツからマンハッタンのMLS本部まで通うため、古い中古車を$500で購入し、雪が降る時でも3時間以上運転して通ったという。
実はその卒論の内容が、現在の中村氏の仕事に繋がっている。幼少期を過ごしたアメリカと、母国の日本。ほぼ同時期に立ち上がったリーグを互いに持ち、CONCACAF(北中米・カリブ海サッカー連盟)のリーダーであるアメリカと、AFC(アジアサッカー連盟)のリーダーである日本。
「この二つのサッカーをくっつけられないかな、と思ったのが発端です。もう少し視野を広げると、オーストラリアも韓国も中国も東南アジアも新しいリーグばかりで、この地域が最後に開発できるラストマーケット。ここを制した者が、ヨーロッパと南米に続くサッカー界3つ目の勢力を作れるんじゃないか。そういう夢を、若い大学院生の僕は思ったんです」

卒論を書き終え、MLSへの就職希望を彼に伝えると、「とりあえずインターンから」という返答。無給ではあるものの、MLSに足を踏み入れることに成功した。
当然ながら中村氏以外にも多くのインターンがいる。厳しい競争に勝つため、午前中に仕事を終わらせ、午後は様々な部署に顔を出して手伝う、という試みを始めた。しかし、大きな壁にぶつかったという。
「はじめはアメリカ人に勝とうとしていて。英語をもっと上手くならなきゃ、彼らの文化を真似しなきゃ、と。でも、勝てるわけがないんです。英語も文化も、その他諸々も含めて。たとえば、日本にタイ人が来ても、“日本人”という括りでは勝てない。それと一緒で、『これは不可能だ』と絶望したんですが、逆にひっくり返せば、彼らが日本人に勝てない部分もある。この人生は日本人として生まれているので、日本人としてどういうバリューを出せるのか、と切り替えました」
その発想の転換が追い風になった。インターンという立場にありながら休暇を申請し、日本に一時帰国(会社からは「勝手に休めば」という返答だったそう)。「MLSに興味ないですか?」という営業文句で様々な人と会って話し、それを土産としてアメリカに戻り、卒論のアドバイザーになってくれた国際部の上司に直談判した。
「僕はアメリカ人に比べれば英語も不得意ですし、ビザを取るための弁護士や、ビザ申請代のお金など、雇うには面倒な手続きがあります。全部知っていますけど、ここにいるアメリカ人にはないものを提供するので、雇ってください」
そのプレゼンが上司の胸に届き、MLSで働き始めることに。ここから華々しい日々がスタート…かと思いきや、中村氏を待ち受けていたのは、自分を雇ってくれた国際部の上司からの“不可解な指示”だった。
「とにかく解せない仕事しかくれなかったんです。『試合会場のボランティアの後ろをずっと付いていけ』とか、『試合会場の受付口で、チケットのリストバンドをひたすら渡せ』とか」
その状況に耐えかねた中村氏は、「卒論の内容を知っているよね?この仕事は何?余計なお金を払ってまで雇ったのにいじめですか?」と上司に聞いてみた。帰ってきた返事はこうだ。
「卒論は読んでいる。ハワイの大会がやりたいんだろ?今すぐやれって言って、できるか?一番下っ端のアルバイトの仕事からいま見せてんだろ。お前がいつかその大会の責任者になった時に、どういう人たちが現場にいて、一番下っ端のアルバイトがなにをやっているかまで知っていないと無理だろ」
上司の親心を知り、「すみませんでした。これからきっちりとやります」と謝罪したと、中村氏は笑う。その上司が部内のスタッフに説いていた“80%20%の法則”も、大きな指針になった。
「80%は会社が言ったことをやれ。20%は自分のドリームプロジェクトを作って、それをどう組み立てるかを考えて、俺のところに持ってこい。それが絶対に無理な時は、『諦めろ。次のドリームはなんだ?』って伝えるけど、フィードバックをあげる限りは、もっと昇華させていってくれ」
バルサのアメリカツアーのプロジェクトマネジャーを担当し、テキサスでは観客動員記録を更新。イングランド代表をはじめとする様々なチームのアメリカツアーを150試合近くも手掛けるなど、“80%の会社の業務”で中村氏は着実に成果を上げていった。
そして“残りの20%”のドリームプロジェクトである『パンパシフィックチャンピオンシップ』(当時の名称)も、ようやく開催まで漕ぎ着けることに成功。日本のJリーグ、オーストラリアのAリーグに足を運び、アメリカを含めた環太平洋の三角形が完成。会場として選んだハワイにも飛び、話をつけた。
「当時、MLS本部にはアジアのサッカーを懐疑的に見る人もいて、大会のスポンサーも自分で探さなきゃいけないような状況で。上司からは『失敗したら“サムライ対カンガルーの大会”って揶揄されるんだぞ。お前はそれを本気でできんのか?』とか言われていたんですけど、ベッカムが所属するロサンゼルス·ギャラクシーの出場交渉も上手くいき、結果的に大成功して」
だが、大成功してしまったが故に、AEGという会社が大会権利の買い取りを希望。愛する我が子をヨソに売られてしまった中村氏は、その後1年間 MLSで働いた後、新しい活躍の場をスペイン·バルセロナに求めた。
サッカーに詳しくない人でも知っている“FCバルセロナ”というメガクラブ。そのクラブの一員として働くことは、どんな経験をもたらしたのだろう。
「期間は短かったんですけど、ヨーロッパサッカーの真髄という感じで、すごくいい経験でした。とにかくすべてが“カタルーニャ”。歴史的に見ても、フランコ政権の圧政時代も、唯一カンプ·ノウの中だけカタラン語が使えたわけです。彼らにしてみれば『今週末負けたね』じゃなくて、『マジで何やってんだよ!』なんです。クラブとしても『アメリカで使われるようなプロモーションなんて必要ない。サッカーを観るためにカンプ·ノウに集まることこそが価値なんだ』と」

バルサでは北米·アジア·オセアニア地域を担当。ひたすら出張し、交渉した。
「本部からは『バルサなんだから強気で、高額でいけ』と言われる。つまり、アメリカはロジックで動きますけど、ヨーロッパはエモーションなんです。それがすごく勉強になりました」
1年半ほどバルサで働いた後、知り合いのスポーツマーケティングの会社から声がかかり、サッカー事業を立ち上げた。
「そこで初めて、自分で会社をやる時ってこう回すもんなんだ、ということや、発想を出していかないと死んでしまう、ということを学びました。その環境にもすごく感謝していますね
キャリアを通じて「海外のサッカーを日本に売ってきた」中村氏。自らの歩みを振り返り、中村氏はあることを決意した。
「MLSではアメリカ人たちが『いま世界一イケてるサッカーリーグでやっている』という誇りを持って仕事をしていて、僕は外様で、それが羨ましかった。バルサでは“自分たちのシンボル”というものに誇りを持って働いている人たちを見て、僕は外様で、それが羨ましいな、と。デル·ピエロのツアーをやった時も、そこの事務所の人たちは『イタリアの神様と働いている』という誇りを持っていた。僕はこの人生は日本人として死ぬ。これまで国際畑でやってきたものを踏まえて、日本のサッカー·スポーツを世界にどう出すのか。同時に、アメリカとヨーロッパのスポーツビジネスのメソッド·原理原則を、どう日本に還元できるのか。そう思って、2015年にBlue Unitedを作りました」
『デロイト トーマツ コンサルティング』とのアライアンスや、『鹿島アントラーズ』のNYオフィス設立。『ヤンマー』と『レッドブルグループ』提携のマネジメントに、『ぴあ株式会社』が主催する『PIA Sports Business Program』の講師·カリキュラム作り。その他にも、中学校時代からの先輩である元日本代表の山田卓也氏と一緒にeスポーツチーム『BLUE UNITED eFC powered by Manchester City』の創設·運営を行うなど、Blue Unitedの動きは実に多岐に渡る。
「言葉の違いだけじゃなく、商習慣やニュアンスの違いまで踏まえて、サービスを提供することが大事だと思っています。『海外がいい』ではない。『海外でそれがトレンドになっている理由、原理原則はこれです』というのを日本に持ってきたら、それを日本流にどうアレンジできるかが大事なんです」
長年の目標である“あの大会”も会社設立の大きな目的だという。
「パシフィック·リム·カップがずっと放置されていて、『誰かやってくれませんか?』と言っていたんですけど、それだとみんなやらないので、『自分でリスクを取ろう』と。ちょうど39歳で、前の会社には迷惑をかけたんですけど、『40歳になる前に起業しないとできない』と思い、独立させてもらったんです」
2018年に『パシフィック·リム·カップ』をハワイで復活させ、翌年も続けて開催。コロナ禍の影響で2020~2021年は開催を見送ったが、2022年と今年は子供向けのクリニックという形で開催した。来年は女子サッカーの大会として復活させるべく、準備を進めている。

中村氏のように海外で活躍するにはどうすればいいのか、アドバイスを聞いてみた。
「まず、やりたいと思ったらやってみる。考えちゃう人が多いと思うんで、第一歩を踏み出すこと。言葉でつまずく人も結構いるんですけど、言葉って完璧には絶対にならないし、僕の日本語も完璧じゃない。『もっと上手くなってから』ってよく言いますが、『それっていつ?』っていう話ですよね。だったら今やっちゃったほうが、もっと早く身に付く
インタビュー途中で出てきた“死”というキーワードも意識すべきことだと語る。
「どうせ死ぬ、ということをすごく認識しなきゃいけなくて。たとえば60歳まで体がシャキシャキ動く場合、僕は47歳だからあと13年。一つのことを成し遂げるのに大体3年なんで、あと4 つの夢しか叶わないんです。そう考えるとやばいと思って、東大の研究室に通っていることも含め、いまもすごく詰め込んでいます。“必ず死ぬ”ということを念頭に置いて逆算すると、意外と待っていられないとは思いますね」
スポーツビジネスという概念が確立されていなかった日本を飛び出し、道を切り拓いてきた。MLS、バルサ、会社設立。困難な目標を成し遂げるために、どんな考え方で進んできたのだろう。
「10歳の時の夢と、20歳の時の夢、30歳、40歳、みんな変わるじゃないですか。なぜなら、それだけみんな視野が広がって、価値観が広がって、環境も変わって、読む物も変わって、付き合う人も変わるから。これが成長の証で、なるべく価値観が変わるように色々なことに興味を持つことが大切だと思います。それに基づいて『僕はこうなりたいんだ』と言って、その環境に進んで常識化すれば、そうなっていると信じています。プロ選手も、それが常識化できている人がプロになっている。『君うまいね、プロになれるよ』と言われて、プロになる人は『当たり前だよね』と信じ続けて、行動が自然と伴ってプロになれるわけです。『自分はこういうことをするんだ』ということを常識化すると、自分の行動も伴い、実現できるはず。でも『できないかもな』と思った瞬間に行動も止まり、できないんです。どれだけ自分を信用して、目標を常識化するか。なにか自分の夢を語って、多くの人が『そうだね』って言うものは大したことがなくて、ハードルが低い。『無理だろ』って笑われる場合はチャンスがある。自分も数えきれないほど人に笑われましたけど、だからこそチャンスだと考えてそこに飛び込んで、どんどん進んでいくんです」
PROFILE
中村 武彦(Takehiko Nakamura)
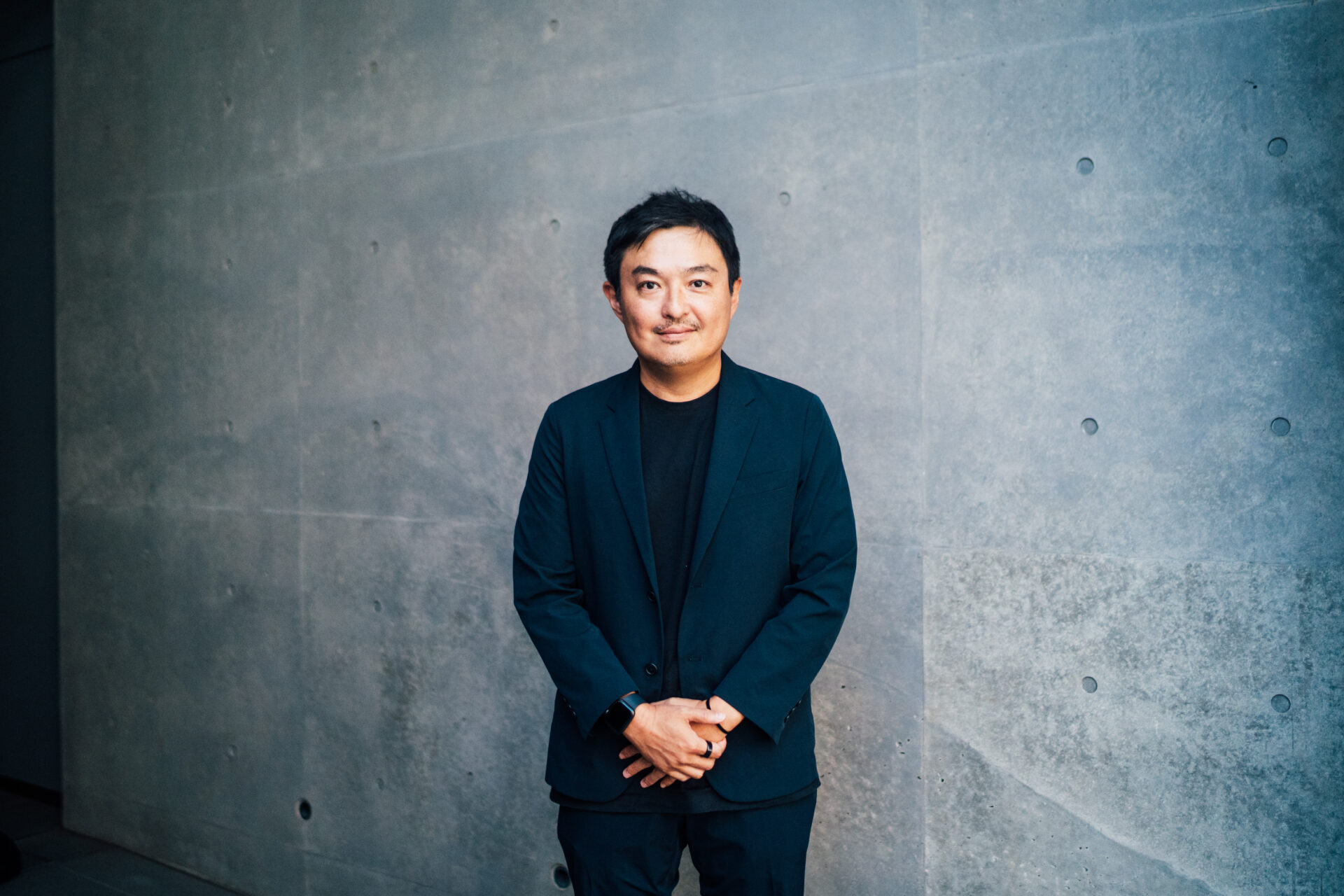
著者
佐藤 麻水(Aaami Sato)

































