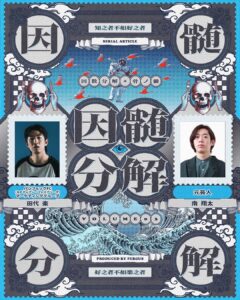iPhoneの絵文字
あまりにも黄色が黄色すぎやしないか。タイピングしている手を何度見直しても自分の手の色は1番ひだりのだいだい色に見えるものだが、我々の肌は世界的に見ればこんなに黄色いのか。黄色いなら黄色いなりに、いや確かに黄色人種であることは自覚しているしそこになんの疑問も持たないのだけど、我々の認識している黄色と、全世界で使用されていて外国人すら「EMOJI」と発語する日本発祥のコミュニケーション手段においての黄色の認識があまりにも乖離してはいないだろうか。そもそもこの文章どうでもよすぎないか。
という、いかにも小僧が書きそうな ”オモシロ” 文章を下書きに書き留めていたことすらすっかり忘れていたいま、A24の『GET OUT』を恋人のすすめで観た。もう26年も自分と付き合っていると「死ぬほど映画や本を読みまくって考察したい時期」と「死んだかのようにネットの海を彷徨う時期」があることを自覚する。最近はビクトリアも寒いし暗いし金ないしそもそもオフシーズンだし後者だった。その結果さらば青春の光のYouTubeをほとんど観て東ブクロのゴルフ学校をほとんど観て代官山メロンをほとんど観たところでそんな生活にちょっと飽きてきた頃に観た、アカデミー脚本賞。
話を要約すると、黒人の身体を羨む白人老人を対象にある白人一家が黒人の身体に白人の意識を入れ込む仕組みを作り、それをオークションで募集するみたいな仕組みである。白人の老人があつまってお茶しながら黒人の身体を見定めるシーンは不気味である。
”アメリカ”っぽい一家でおこる、なんとも”アメリカ”っぽい社会風刺を意図したこの作品にひとりだけ日本人が登場する。タナカと名乗るその男性は日本語のアクセントを用いて黒人の身体を競にかける白人と同じ立ち位置で登場し、白人と同じレイヤーで描かれている。
強烈な違和感を感じた。
ロサンゼルスに住んでいたとき、どちらかと言うとヒスパニックや黒人文化に親しみを感じ、ときに資本主義なアメリカ社会について彼らが批判的な表現をしていることを同じ目線で捉えていた。それは少なからず僕が ”外国人” として北米で生きてきて、国籍がないことのマイノリティと人種的なマイノリティを感じていたからである。そもそもロサンゼルスはスペイン語が通じるくらいその人種が多かったのもあるけれど、どこか ”白人でない” ことによってポジションを確保していたことは確かなのだ。
だから強烈な違和感を感じた。
その作品で描かれる ”日本人” は自分が自覚しているポジションの逆サイでいかにも ”日本人” っぽい気品でゆっくりと話し、知的な様子で描かれていた。監督ジョーダンピールのインタビューに日本人がでた背景としてこう書かれている。
「タナカはマイノリティーだが、白人エリートの文化に受け入れられ、彼自身も溶け込み、カネもある。そうした『モデル・マイノリティー』を描こうという考えからだった」。
https://globe.asahi.com/article/11532864
つまり白人社会、アメリカ視点からみた日本人は「確かにアジア人で有色人種でときには差別の対象になっているかもしれないけれど、基本は成功していて白人と同じ立ち位置にいる(かのようにふるまっている)よね」である。
恐怖を感じた。
冒頭の文章が下書きからひっぱり出されたとき、自分の ”オモシロ” 文章のなかに
タイピングしている手を何度見直しても自分の手の色は1番ひだりのだいだい色に見えるものだが、我々の肌は世界的に見ればこんなに黄色いのか。
とあったからである。
多分上記の文章を書いたときには口をあけてぼーっと書いていたに違いないが、潜在的に「いや他のアジア人とは違うでしょ」的な思考があった可能性だってある。それはなぜかみんな乗っている日本車が、なぜか最強のパスポートが、なぜかみんな1度は行きたいと口にする東京が文字を打ったのかもしれない。そしてそれを付け合わせ的に描いた作品がアカデミー脚本賞を受賞した事実がそれを証明しているかもしれない。
日本人とはなんなんだろうか。少し考えるきっかけになった。
今日もビクトリアは肌寒く、悴んだ手はすっかり白くなっていた。
スタジアムで起こっている事象を
スタジアムだけで完結できない時点でお前はイケていないよ、とそんな当たり前のことがSNSの登場によってぶっ壊れている様子を見ると、半年ROMるって文化は超絶有効なルールだったことを全3シーズンに渡って描いたドラマ「エミリーインパリス」の続編はいつなのでしょうか。
陽平くんと
話した。恋人が日本からきてくれて赤道ギニアの真夏かなと思うくらいにアッツアツッ♡な日々を過ごしていたときにカズキオカモトから連絡がきた。
「高丘選手にインタビューしてほしいんだ。ガクくんの経験でしか聞けないことがあると思って。」
恋人に尋ねた。少しだけ時間をもらってもよいかと。
案の定空気は青道ギニアになった。
具体的な記事の内容は現在絶賛編集中の本編をご覧いただきたいのだが、その中でかなり興味深かったのは「北米はクラブスタッフがストーリーを作る話」だった。どういうことか。
ご存知のとおり、Jリーグには幾多のストーリーが展開されている。例えばアカデミー育ちの地元の少年がトップチームと契約する、なんてのは当事者以外がリリースだけ読めば「ふーんそうか」なものだが本当に深くクラブを愛する地域住民やスタッフからすれば感慨深いなんてものではない。そしてそんな少年が世界に渡ることもあれば絶対にないと思っていた同じ街のライバルクラブにタダで移籍したりもする。あぁフットボールとはなんて生臭いのだろうか。
もっとミクロな話をすると、例えば直近の大一番に向けてクラブとしてどんなプロモーションをしていこうか、どんな露出をしていこうかなんて話にも繋がる。ここでは陽平くんとの話のなかで、PKを外した選手の該当シーンをあえてSNSに投稿し、そこからの再起を描きたいスタッフに対して選手から不満がでたとのことが思考のきっかけになる。ここは北米、我々がいるのはカナダでアメリカにくらべればその文化は薄いかもしれないが、ショービジネスや魅せることそのものに関してかなりの知見と金銭が投資されていることには違いがない。そして当たり前に ”その作られた魅せもの” をマンキンで楽しむことのできる国民性がある。
陽平くんの話における問題点は「ただスタッフと選手で”この件に関する”方向性と露出方法が握れていなかった」だけだと思うのだが、そもそも論としてクラブスタッフ側の裁量に『在籍選手をどう魅せるかをある程度演出する』があること自体がとんでもないカルチャーショックであった。僕の経験ではあくまで選手の言動や行動に対してサポート的な形でグッズを作成したり企画を乗っけたりすることはあった。が、そもそもの「売り方」をクラブが決めていき選手よりも強い立場で指示(提案)することができるなんて超MLSである。興奮した。
日本の格闘技では昔から団体側がその選手の売り方やポジションを設計している。ひと昔まえのPRIDEやDREAMでは佐藤映像の制作する煽りVにその売り方が集約され、選手入場の前に「この選手はこういう特徴があるからこの見方をすればいいのね」と客がある程度理解できる仕組みになっていた。だから五味隆典はいつだって強敵を倒すジャパニーズヒーローだったし、青木真也は捻くれていながらどこか人間味のあるファイター像だった。
RIZINの立ち上げとともにSNSが発達し、選手がメディアを持つ時代がきた。そして生まれたのが朝倉未来なのだが、それよりも個人的にカリスマ性を感じる平本蓮がいる。平本選手はSNSでライバルファイターに絡み、ニュースをつくり、選手としての注目度を高めた。かつては記者会見の場でのみ行われたトラッシュトークがいまは選手発信でフレキシブルに行われる。もちろんその自由奔放な発言の数々も団体は把握しており、選手としてのポジションが団体の意思決定と選手の合意のもとで配置されている。日本の興行において、このやり方をできるのは格闘技しかないと思っていた。それは「競技の特性的に言動に行動が伴いやすい」ことと「個人競技であるために本番までに矛盾を感じにくい」ことにある。
そんな個人的な常識を覆しうる陽平くんの発言だった。例えばこのゴールキーパーは生意気でいつも相手を挑発する感じでいこうってことがもしかしたら行われているかもしれない。
そこで最大の疑問が浮上した。はたしてそれに観客はノレるのだろうか。
例えば1ヶ月後にダービーマッチがあるとして、選手が露骨にライバルクラブをトラッシュトークとして侮辱するような発言を行うことって ”日本では” どう受け入れられるのだろうかと思った。僕自身はそれはそれでありだなと思うし、いまの日本サッカー界に蔓延る「たとえダービーでもお互いをリスペクトして仲良くしましょうね」なフワッとGPA3.5っぽい風潮に切り込みをいれることは将来のために必要なことだとも思っている。
LAFCとLAギャラクシーのエル・トラフィコでは選手だけでなくクラブスタッフもSNSに人格を有しているので、日本人からみて若干過剰かな?と思われる表現がダービー前にドコドコ行われていたりしてそれはそれで新鮮だった。それはいかにも二本指でのアメリカっぽい表現だが、元を辿ればそのアメリカっぽいトラッシュトークは日本のプロレス・格闘技に起因している気もするし、この市場にそれらの表現を受け入れる土壌だってあるはずだ。
さてクラブがストーリーを作る問題、あなたはどう感じるだろうか。本当に気になる。
せっかくここまで読んでくださったのだから、Twitterで教えてほしいと思うんでちゅわ
(とっとこハム太郎リボンちゃんより絶対にいらなかった語尾抜粋)
カリスマだった。
いやどう考えても。
フットボールクラブには色がある。その色を作るのは選手か、監督か、それとも。
2021年年末。新卒3年目を迎えた僕の前に、その会社に色を塗りたくった大御所が立っていた。
肘タッチ。
肘タッチだった。初コミュニケーション肘タッチ。そして彼は言った。
「お前が楽かぁ。威勢いいらしいじゃん。」
おしっこを漏らした。それは大学4年のサークルの先輩が夏合宿で千葉の奥のホテルの宴会場で調子に乗った1年をしばく前に発する言葉である。そもそもその場で紹介してくれたのは僕の直属の上司だったわけだが「威勢がいい」で台所にのせるってどういうことなのと今これを書いていて思った。
だがしかしその威勢エビは見事なまでにそのカリスマ性にゾッコンになった。
東京で生まれ育ち、東京のクラブを愛する自分は、どの意味でこのクラブに好意的になるのだろうとずっと感じていたからだ。モチベーションに大きく左右するそれを「この人と働きたい」の一点だけで突破できることを教示してくれた姿勢。「フットボールクラブはカッコよくあるべき!」と声だけ大きかった自分に「そのカッコいいとはなにか」を考えるきっかけをくれた。
最初は正直ついていくことでいっぱいいっぱいだった。こんなにも泥臭いのかと思った。大学で教わること、スポーツビジネスセミナーで理論展開されていることがいかに実用的でないかをまざまざと思い知った。スタジアムでファンが通る道の水たまりを素足でどかす意味なんて座学で学べるわけがなかった。
ぶっ飛んでいると言われる仕掛けのなかにはロジックがあった。そこに真摯に地域を愛することが重要な項目として掲げられ、ローカルのためにならないフットボールクラブなんて意味がないことが神経に刻まれた。企画なんてひとりじゃないと生みだせないことも、企画なんてひとりじゃなにも実現できないことも、声に出せば意外となんだってできることも、できるだけYahoo!ニュースでは炎上しない方がいいこともすべていい経験だった。
ついていくことで必死だった日々に少し余裕ができたころ、次第にこのひとを笑わせたいかもと不思議な感情が芽生えた。指示をこなすだけでなく、自分の生きてきた経験を少し引用してみたくなった。
黙ってタイで選手紹介を撮ったときも、憲剛さんが踊ったときも、スタジアムで大仁田が電流爆破しようとしたときも、大八木監督がリンカーンの芸人大運動会っぽくなったときも、天童よしみさんが激しく無駄遣いされたときも、全部笑ってくれた。楽しかった。嬉しかった。だからもうクラブを離れようと思った。
かっこいい人には理由があるし、愛されるものにはワケがある。
それを外から分析することは簡単な時代になったけれど、本当のことは内部しかわからない。だからいつまでも地に足つけてやるべきことをやりたいなと思う。いつかいい報告ができるように。
天野乙。
感謝と尊敬をこめて。本当にお疲れさまでした。
PROFILE
田代 楽