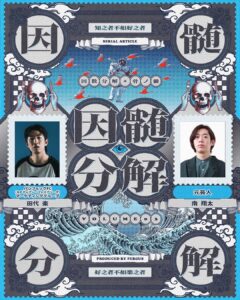街で着れるユニフォームじゃなくて、ユニフォームを着れる街を作った方がいいんじゃないか | 2025 Pacific FC Home Kitローンチ
田代楽が海をわたり、2年が経とうとしている。
昨年に引き続き、彼が手掛けた2回目となるユニフォームローンチが行われ、自らコンセプトメイキング、映像、写真撮影まで行ったこの企画に込められた想いを、ぜひご覧ください。
“クラブや選手をいかにスタジアムと練習場の外に出すか”っていうのは、すごく大事

クラブとしてビクトリアの街中でユニフォームのお披露目会をやるというのは今回が初めてだったそうですが、イベントの概要と反響について教えてもらえますか?

ビクトリアのダウンタウンにある広場を貸し切ってユニフォームのお披露目会をやりました。ダウンタウンに住んでいる人はもちろん、去年のユニフォームローンチの映像で協力してくれたヴィンテージショップが今回はポップアップで出店してくれたり、選手も全員来てくれました。僕の中で“クラブや選手をいかにスタジアムと練習場の外に出すか”っていうのは、すごく大事だなと思っていて。

たとえばフロンターレのときやケンゴさん(中村憲剛)の引退試合でも意識していたんですけど、街にどれくらい選手を連れて行けるか、って改めてやっぱり大事だなと今回のイベントを通してあらためて感じました。

それができるかどうかって、街との関係性を表すと思うんです。今回のイベントも、そういう繋がりがあったから広場を使って実施できたし、地域に根を張っているスタッフがいないと、そういうことって実現できないなって。

SNSでの発信が主流になっているなかで、リアルな場でのお披露目にはどんな意図がありますか?

SNSでの発信も重要ですが、なにかのお披露目をクラブ内だけでやらずに、シンボリックな場所、ランドマーク的なところでやるほうが情報が拡散されるよなっていう感覚はあります。

イベントを終えて、選手たちの反応はどうでしたか?

選手たちも現地で、ファンとか地域の人、ビクトリアに住んでいる人たちと触れ合っていて。うちのクラブはファミリーチームで、規模も小さいですしファンとの距離が近い。だから、それはすごく良いことだなと思って見てました。

カナダの人たちは、日本と比べてどういう反応の仕方をしますか?日本だとXで良くも悪くも反応がありますが。

SNSに関していえば、カナダはインスタがメインですね。うちも一番注力してるのはインスタです。ただ、英語特有なのか国民性なのかはわからないんですけど、ネット上で議論する文化はあまり見ないですね。リアクションはあるんだけど、不毛だなって思われてる空気があります。

うちのクラブは練習も公開してるし、普通にスタジアムで練習したりするんですよ。ファンが見に来ることもあるし、コールリーダーとは週に2〜3回会うこともあるんですよね。そのときに、公開する映像について意見を聞いたり、『今度こういうことやろうと思ってるんだ』っていう話をしています。

シーズンチケットホルダーの方も、クラブのオフィスに来てチケット担当者と喋ったりするんですよ。負けが続くとファンが『あいつを出せよ!』って文句を言ったりすることもあります(笑)。でもやっぱり、“リアルで言わないとなにも動かない”っていう空気は、みんな理解してると思います。

リアルでの接点が日常的にあるんですね。

そうですね。去年負けが続いた時はインスタでネガティブなコメントが来たりするんですけど、そういう時は逆にシーズンチケットホルダー向けにパンケーキを食べる朝活イベントをやったりしました。要は対話する場を設けました。

みんなあんまりSNSでの声を気にしていないというか、“過剰に何か言ってるやつは変なやつ”って認識だと思います。日本だとそういう声を無視してはいけない空気がある気がしてて。それって日本独特かもしれないですよね。たしかにひとつの声ではあるんだけど、それよりも現場で起こってることの方が大事だと思います。


「サッカーを好きな人がどうしてサッカーを好きなのか、その個人の理由を探るのが一番面白い」

最初にセカンドキットを発表してからファーストキットを出す形になりましたが、改めてセカンドキットを先に発表した理由を簡潔に教えていただけますか?

セカンドキットを先に出した理由は、前回の記事にも書いた通り、ユース出身のサミという選手のパスウェイと映像、制作物を全て同じタイミングに合わせる流れがあったからです。

セカンドキットとファーストキットの違いを教えていただけますか?

ホームキットに関しては、数年間デザインを大きく変えていないんですよ。今回はクラブカラーのパープルにエンボス加工で、クラブに由来する柄である波を入れるという形にしました。

コンセプトはどうだったのでしょうか?

去年と同じですね。「街でどうフットボールが浸透しているか」というテーマで、そういった人たちをピックアップする、という狭いコミュニケーションを選びました。

映像の作り方に関してはどうでしたか?

去年の映像は、ユニフォームをトスして街でいろんな人が登場する構成でした。今年はもう少しパーソナルに踏み込みました。個々の選手や監督、サポーター、ラジオパーソナリティーなど、地域の人たちがどういう思いでこのクラブを応援しているのか、どういう思いでこの街を愛しているのかを、2分程度のミュージックビデオのような形で表現しました。

こだわった点について教えていただけますか?

僕の友達に国内外のファン文化に精通している子がいて、「サッカーを好きな人がどうしてサッカーを好きなのか、その個人の理由を探るのが一番面白い」という軸でポッドキャストを始めたんですね。僕も実際に出演したことがあるのですが、たしかにすごく面白いなと思っていて。その価値観を一般化する必要はないけれど、個々の理由を記録しておくのはすごく意味があると思いました。

いろんな立場の人たちが、なにかしらクラブを応援する理由、またはこの街に留まっている理由があるということを、映像を通して出そうと考えました。

印象に残ったエピソードや興味深かった人はいましたか?

印象的だったのはラジオパーソナリティーの方が話していた内容です。クラブやコミュニティが島の子どもたちに向けていろいろなプログラムを展開していることに対して、すごく感謝していると話してくれていて。

また、女性の方は「これまでユースのサッカーに触れようと思ったら、バンクーバーまで行かないといけなかった。でも今この街でできていることには、やりがいもあるし、本当に意味のあることだと思っている」と言ってくれたんです。

これ、台本なしでやったインタビューなんですけど、やってる側と受けている側が、同じ意図とか感覚を持ってるように感じられて。それがすごく良かったなと思いました。

サッカークラブを愛する理由 | 「俺はこの街が好きだ」

「帰属意識」って、よく言われるじゃないですか。サッカークラブって、結局「俺はこの島が好きだ」とか、「俺はこの街が好きだ」っていう、それだけだと思ってるんです。それ以上になにかを縛り付けるような理由って、実はそんなにないと思うんですよ。

たとえばJリーグ的な観点で言えば「推し活」とかいろんな切り口でファンをつくるというのがあるじゃないですか。でももっと広い視点で見たら、「この街が好きです」っていうピュアな感情以外にないなって思うんです。

だからこそ、この「街を愛する」というテーマはホームキットのローンチにはずっと使えるなと思っていて。ずらさなくていい要素だと思うし、そこはあえて冒険しなくてもいい。セカンドキットの方で遊べばいいんじゃないかなっていう感覚ですね。
ブランドをつくる | “ブレないこと”の恩恵

ファーストキットのデザインは基本的にどのクラブもチームカラーに合わせて細かいところだけ変えていますよね。これって「販売する」側面から見た時にどのクラブも難しい課題だと思っていまして。今言ってくれたように、セカンドは遊んだりとか、いろんなメッセージを伝えたりっていうスタンスでリリースできるけど、ファーストはあんまり変わらない。結局、デザインが変わらないのにどうやって売るんだ、みたいな。

それは間違いなくそうだと思うんだけど、ぼくは少し異なる考え方も持っています。一つは、“ブレないこと”の恩恵。それがいわゆるブランドみたいなものを作っていくことになると思います。

例えば、パープルで、エンボス加工っていうのをブレないで、数年続けていくことによって、“ホームキットとは何なのか”とか、“クラブのファーストユニフォームって何なのか”みたいな軸がひとつできてくると思うんですね。で、それを今後数年間で裏切ることもできるし、継続することもできる。要は“軸を作ってきてる段階”だと思ってるんで、それはそれでアリだなって思う。

で、売り方に関して言うと、それはどっちかっていうとデザインよりも“コミュニケーション”とか、“販売方法”なのかなと思ってるんです。これはホームキットじゃないんでちょっとあれなんですけど、セカンドキットは、胸スポンサーのテラスと協業して、1本売れるごとに子どもたちに数ドル寄付されますとか。要は、“購入すること”がデザイン目的でなくて、街の支援とかそういった意味をユニフォームに付け加える形です。もっと言えば、別にデザインが変わってなくても買う人は全然いるなって。例えばボカとかリーベル・プレートのホームキットって、ほとんど変わってないと思いますし、それでもマーチャンダイズの売上があるってことは、それだけ“密なコミュニケーション”があるんだと思います。要するに、伝え方となにを伝えるかが大事なんだと。しかも、それってたぶん“デジタルのコミュニケーション”だけでは絶対に動かないって思ってて。例えば、カズキくん(FERGUS)がなにかのデザインを担当した時に、『こういう意図でやったから買って』って直接言われたら、ぼくは買います。そういう関係性ですから。でもそれを、カズキくんのSNSを見ただけではすぐに購入するかはわからない。この“関係性”をいかに、一人一人のスタッフがいろんな人と作るかで前述の問題は解決できる気はします。

お披露目会の時にそういったコミュニケーションは見受けられましたか?

選手とか監督も来てたんですけど、選手がサポーターに『良かったら俺のユニフォーム買ってよ』みたいなコミュニケーションはしていました。もちろんそれは冗談まじりだけど、でもやっぱりその人は買っていました。昨日、ホームスタジアムで開幕戦だったんですけど、その人はユニフォーム着てたんですよね。まあ、押し売りといえば押し売りなんだけど(笑)。でもその“関係性”を選手と作れてるっていうのは、それはそれで一つの、なんて言うんだろう……ありなコミュニケーションだな、とも思います。

SNSで伝えることには限界がありますか?

デジタル(SNS)は情報伝達としてはすごく優秀だと思うんだけど…。僕も結局デジタルで仕事してるし、うちのクラブも結構デジタルを使ってる部分ももちろんあるんですけど、本当に“人に行動を起こさせる”とか、“泣かせる”みたいなことをするには、すごく難しいなと感じています。例えば、写真展で印象的な写真があったら、みんな感動すると思うんだけど、デバイス上だけでは…みたいな話です。あれだけ集客力があるだろうモナリザですら別に検索したらみんな見れるわけで。そう考えると“アナログなイベント”の方が、手間はかかるけど速いんですよね。

昨今のサッカークラブにおけるアパレル事情についてはどう見ていますか?

あれこそ、ファンとのコミュニケーション不足が如実に表れているような気がします。うちのクラブでも一番売れるのって、クラブのロゴがドーンみたいなやつなんですよ。結局ファンはそれを求めてるんですよね。また憲剛さんの話で申し訳ないんですけど、憲剛さんの選挙カーのやつをやった時も、今回のお披露目の時も、ファンは試合観戦のときと同じようにユニフォームとかクラブのウェアとか、スカーフとか、纏ってくるんですよ。

“街にクラブのロゴを出したい”みたいな発想で、ああいうスタイリッシュなものを作るんだったら、街で何かイベントをやった方がいいと思います。例えば、シーズン途中で加入した選手のお披露目を駅前でやるみたいな。クラブのロゴを纏ったファンが街中に100人でも集まれば相当なインパクトにもなりますし、それに合わせて何かグッズを作るというのもいいかもしれないです。以前、『football a go go』でNanaseさんと“街で着れるユニフォームじゃなくて、ユニフォームを着れる街を作った方がいいんじゃないか”みたいな話をしていたことがあるんだけど、まさにそうですよね。

「ダメだけど、別にいいよね」の中にしか面白さって詰まっていない

あと、うちのクラブって、何組か団体があって。団体っていうか、サポーターのコミュニティみたいなのがあるんですよね。で、そこで自分たちのオリジナルユニフォームを作ってるんです。もちろんオフィシャルのユニフォームをみんな買ってはいるんですけど、それとは別で、Tシャツを作ったり、スカーフを作ったり、アンオフィシャルと言われるものを自由に作って売ってるんですよね。おもしろいのはそれをオフィシャルショップの横で販売しているんです。

それに対してクラブはどう見ているんですか?

排除するとか、「公式のグッズと競合するんじゃない?」みたいな視点は、あまりないですかね。たしかに、オフィシャルグッズを食ってしまう可能性もゼロじゃないですけど、オフィシャルグッズって、エンブレムが付いてたり、選手の番号が入ってたり、そういう“著作っぽい”部分はちゃんと守られてるのでそれはそれでOKなんです。むしろ、そういう自由な創作活動を支持していて、クラブとしても受け入れている。だから、クラブのビジュアル制作物が勝手に増えていくんですよね。これはすごくありがたいと感じています。

小さいクラブなので、僕らが全部のグッズを作り切るのは無理なので、みんながある程度のルールの中で、それもかなり緩いルールの中で自由に動けるようにしています。「ダメだけど、別にいいよね」の中にしか面白さって詰まっていないと思ってて。ただ一方で、グレーなものって黒になっちゃうので、そこは難しいなとも思うんですよね。
PROFILE
田代 楽(Gaku Tashiro)