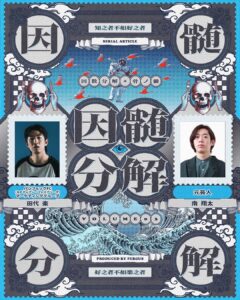鈴木大地氏のライフキネティックトレーニングを終え、少しの休憩を挟んだ後にサッカー指導者である吉永一明氏のトレーニングが行われた。
吉永氏は1990年に三菱養和サッカースクールコーチから指導者人生をスタートさせると、アビスパ福岡、清水エスパルス、サガン鳥栖で育成年代からトップまで幅広く指導し、2009年には山梨学院高サッカー部ヘッドコーチに就任。この年に全国高校サッカー選手権大会初優勝に導き、翌年から監督に就任すると、2015年までに前田大然(セルティック)、渡辺剛(KAAヘント)の日本代表選手を輩出した。渡辺をCBにコンバートさせた人物としても知られている。
2016年からヴァンフォーレ甲府のトップチームコーチ、2019年にはアルビレックス新潟の監督も歴任した後、アルビレックス新潟シンガポールの監督を2年半務めた。
指導者として実績も経験も豊富な吉永氏はライフキネティックトレーニングを真剣な眼差しで見つめていた。
筆者は山梨学院高時代から交流があるが、いつも感じるのは勉強熱心であること。新しい考えや自分とは異なる視点を持つ人間に強い興味を持ち、コミュニケーションをとって自身の知見に変えていく。
この日もいいものはすぐに取り入れるという吉永氏らしい姿勢がトレーニングにもにじみ出ていた。
「常に周りを見てサッカーをしましょう。鈴木さんが先ほどおっしゃったように、ただ眺めるだけではなく見て理解をしてプレーしていく。この『見る』を意識してサッカーができるようなトレーニングをしよう」
選手たちの前に立った吉永氏はこう口にすると、see、watch、lookだけではなく、見た上でanalyze(アナライズ=分析する、分解する)を含めたトレーニングをスタートさせた。

「失敗を恐れないで積極的にプレーしてほしい」
ミスをしない慎重なプレーをするのではなく、積極的に能動的に取り組まないと、過去の自分を超えることができない。吉永氏はトレーニングを通じてこの言葉を常に発し、まずは選手たちに前向きな姿勢を促し続けた。
まずはウォーミングアップ。5人1組になってそれぞれの正方形のグリッドに入り、パス回しからスタートをした。グリッド内での4vs1。ボール2個をツータッチ以下で回し、ディフェンスがボールをカットして外に出したら、ワンタッチでもう1個のボールを回す。2個とも奪われたら終了だが、ワンタッチパスが10回繋がったら、もう一度ボール2個からのスタート。2つのボールが重なっても終了というユニークな設定だった。
ボールが2つあることによって、常に関節視野を持ってやらないとエラーが生じる。ボール1つであれば、ボールとDF、味方を見ていればこなせるし、極端な話で言うとボールをしっかりと視野に捉えていたら後は感覚でごまかせる。
しかし、2個になった途端に、もう1個のボールを常に間接視野で捉えていないと、ボールを捌いた直後に来るもう1個のボールに反応できないし、ボールがあるところにパスを出してしまって重なってしまうかもしれない。さらにその上でDFの状況と味方の立ち位置も視野に入れて、次のプレーをきちんと予測して、それを連続してできるようにならないと、プレーの質は確実に下がる。
これは前半戦で鈴木氏が行ったライフキネティックトレーニングと狙いは同じだった。普通のボール1個のグリッド内の4vs1でも、意識の高い選手であれば、相手と味方も視野に入れてやろうとするからこそ、マルチタスクになるが、その意識がない選手にとってはマルチタスクにならず、単純なパス作業になってしまう。
だが、ボールが1個増えることで、どの選手にとっても強制的にマルチタスクになる。つまりこのトレーニングも『TYN(=楽しく、予想外で、慣れない)運動』となる。
トレーニングを外から見ていて感じたのは、意識の差がマルチタスクの複雑さの大小を決める指標になるということだ。
前述した通り、意識の高い選手は自分からマルチタスクをどんどん複雑化していって、そこでミスをしたり、悩みながらも、どんどん脳を活性化させていったりして、その先で得た成功体験を自分の力として吸収していく。だが、そうではない選手はいつまでも強制的なマルチタスクをただこなしているだけ。積極的なマルチタスクを行う選手との実力差はこういうトレーニングを重ねれば重ねるほど広がっていくのではないかと感じた瞬間でもあった。
「ただ見るだけじゃダメだよ。見ているだけじゃ仲間と繋がれない。見て感じたことを声に出すことで、声で仲間と繋がることもしないといけないよ」
吉永氏の声かけは的確だった。ボールが1個になった瞬間にも「ワンタッチだよ!」と声を出して仲間に伝えた選手に対しても、「そう、そうやって味方に情報を伝える。伝えてもらった情報をもとにプレーに反映せることも大事だよ」とすかさず声をかけた。
視覚、知覚だけではなく、聴覚も駆使して、『精査→推論→判断』の作業を連続して行う。吉永氏も『認知』を大切にしているのが強く伝わったし、練習中に何度も止めて、シチュエーションを提示してから何を考えるかを問いかける。「これをしなさい」ではなく、「こういうこともできるし、これもできるよ」と答えではなくヒントを与える。吉永氏のコーチングスキルも垣間見ることができた。


次は4人1組を作ってからの4vs4のコートチェンジのポゼッションゲーム。正方形のグリッドを2つ繋げて、片方のグリッドで4vs2をアンダーツータッチで行い、もう1つのグリッドに2人が待機。4vs2の2人の守備者がボールを奪ったらもう1つのグリッドに待つ2人に繋いで、同時にグリッド移動し、奪われた側から2人がグリッド移動して4vs2がスタートする流れだ。
「さっきのトレーニングにトランジション(切り替え)が入ります。さっき鈴木さんがやったお手玉のトレーニングで姿勢の大切さ、どこを見るかを学んだよね?ボールだけ見るのではなく、しっかりと周りを見よう。あと、逆のグリッドでボールを待つ2人は休憩ではないので、常にマイボールになった時にいい状態で受けられるように準備をしてください」
ここも的確な指示が飛ぶ。ライフキネティックトレーニングでやったことを思い出させると共に、動き続けないにしろ、準備を怠ったり、集中を切らせたりすることはその後のプレーに大きな影響を及ぼす。サッカーにはハーフタイム以外休憩時間はないという事実をきちんと伝えた。
さらに吉永氏は守備者にボールを奪い切ること、保持者に奪われても反対のグリッドにボールを行かせないように瞬時に囲い込んだり、パスコースを切ったりすることを求めた。
「試合と同じようにプレーして。実戦から遠ざかるようなプレーはしないこと」
吉永氏はこう言って目を光らせる中、筆者が一番唸った指摘が入った。

学校のグラウンドは近くに稲毛海浜公園があり、この日も強烈な海風が吹き付ける中でトレーニングは行われた。グリッドが飛ばされたり、ボールが動いたりするほどの強風の中、大きな声で注文が飛んだ。
「風も計算に入れてやってほしい。サッカーにおいて重要なのは気候条件もだぞ!」
練習や試合がいつも同じ条件で行われるとは限らない。晴れの日もあれば、雨の日もあるし、風が強かったり、蒸し暑かったりと、気候条件やピッチコンディションは毎回異なる。だからこそ、気候条件なども情報の1つとして頭の中に入れてプレーをすることは非常に重要なことだった。
熱を帯びたトレーニングは3人目の動きを入れた突破へと進み、そこでダイレクトプレーとスピードを維持したラインゴールの突破、その阻止の攻防を繰り広げた後、ラストは紅白戦が行われた。
紅白戦において、吉永氏は1つだけルールを設けた。味方にパスをして、受け手がコントロールをしたらリターンパスは禁止で、必ず違う選手にパスをすること。ただしワンタッチだったらリターンパスOKということだ。
「今日トレーニングでやった3人目の動き、奪われたら奪い返すところをフルパワーでやってください」
パスを出した選手は受け手がコントロールしたら、すぐにリターンを受けるポジションではなく、3人目の動きをサポートする動きや、他の選手へのパスを予測してから自分のポジションを取り直さないといけない。逆に言えばパスを出す時に、ダイレクトで受けられるポジションに行くことも考えないといけない。周りもそこを察知してパスの出し手の代わりにパスを受けに行かないといけないし、声で指示を出して情報を伝えないといけない。たった1つの条件を入れるだけで、選手たちはより思考する。


最後まで頭を使った濃密なトレーニングを終え、吉永氏は選手たちにこうエールを送った。
「今日1日やったことは全てつながっています。急に技術がぐっと上がるわけではない、変化もすぐには現れない。でも、頭を使い続けることで伸びていくと思います。選手たちがサッカーをするわけであって、ピッチ上では指導者ではなく、選手たちで問題を解決しないといけない。だからこそ、選手個々が思考し、もっと声を出して伝えて欲しい。正しい、正しくないは別で、見えているから伝えられるし、勝ちたいから伝える。そういうものがみんなの中で広がって、いい成績を残していく姿を見ていきたいと思っています」
自立、自律した選手になってほしい。個人としてもチームとしても思考が出来、伝達が出来るようになってほしい。そのメッセージは選手たちにきっと伝わったはずだ。

PROFILE
吉永 一明(Kazuaki Yoshinaga)

著者
安藤 隆人(Takahito Ando)