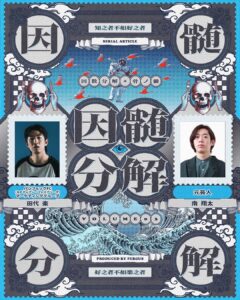フットボールも多角的な観点から分析され、ピッチ上に落とし込もうという動きは近年、活発となっている。そのポイントは多種多彩で、フットボールのメカニズムから派生したものもあれば、人間が本来持つ能力にフォーカスを当てて生態力学、生態心理学、身体機能など幅広いジャンルから派生したものもある。
12月21日に千葉県にある敬愛学園で行われた『Nike FC presented by SOCCER SHOP KAMO』。
オンピッチ(技術面)とオフピッチ(精神面)の両面から選手を育成することを目的としたこのアカデミーの第10回目は、オフピッチの面でこれまでとは異なるアプローチがあった。

講師として招かれたのは鈴木大地氏。
ドイツで盛んに行われている脳科学と運動学などを融合したプログラムがある。脳に適切な刺激を与えることで、思考回路の幅を広げ、より自分が持っている運動能力を発揮できるようにするトレーニングを、日本のサッカーの世界に実践的に取り入れたのが鈴木氏だ。
彼が行ったのは座学ではなく、ジャージ姿でグラウンドに立ち、身体を動かしながら行う脳トレーニングだった。取り組んでいる選手たちも、見ている周りの大人も非常に興味深く、エンターテイメント性も含まれたトレーニングとなった。
「みんなが実現したい技術、戦術を具現化するための脳トレーニングをします。頭脳が活性化されていないと判断ができません。周りをただ見ても分かりませんし、プレーパフォーマンスに反映されません」
ハキハキとした声で選手たちに話し始めた鈴木氏は、いきなり核心から入ったように感じた。
サッカーの世界ではよく「周りを見ろ」と言われるが、ただ『目で見ていろ』ではなく、『見た上で情報をピックアップし、その得た情報をもとにプレー判断に反映させていく』という言葉が含まれている。
つまり『見る』はsee、watch、lookだけではなく、見た上でanalyze(アナライズ、分析する、分解する)も含まれており、ドリブルやパス、ランニングという運動をしながら、脳内では常に情報収集と情報処理を行って、かつそれを瞬時にプレーで表現しないといけない。
「やるべきことが増えるマルチタスクになるほど、脳内の許容量が超えてパンクして、情報収集、情報処理のクオリティーが落ちる。つまりそれがパフォーマンスの低下に直結します。でも、サッカーのピッチ上はマルチタスクの連続だからこそ、普段から知覚、視覚、聴覚と運動を連動させて、マルチタスクできるスペックを脳に兼ね揃えていないといけません」
鈴木氏のトレーニングはまさにマルチタスクを同時進行することで、思考的矛盾や相反する運動を組み入れながら脳内にバグやカオスを生み出して、そこから答えや判断、体の動きを生み出していく。
最初に行ったのは10回腿上げをしながら、両手でそれぞれの腿を叩くこと。鈴木氏が「はい!」と言ったら手をクロスして右手で左腿、左手で右腿を叩く。シンプルな変化だが、それでも困惑する選手が現れる。
さらに「僕が『身体を前に倒してください!』と言ったら、逆の後ろを倒してください」と相反する動きを入れると、さらに選手たちは困惑し、シンプルな腿上げもうまくできなくなる選手が続出した。

「これだけエラーを起こすと、サッカーではもっとエラーを起こすよ!」
鈴木氏の核心を突く言葉がグラウンドに響く。
次は選手の前に右から黄色、青色、オレンジの3つのマーカーを置き、選手は真ん中の青色のマーカーの前に立つ。これがニュートラルの状態となる。そこから①の音と②の音を聞かせ、①の音が鳴ったらオレンジ、②の音が鳴ったら黄色に行くルールにした。
それを少しやった後、今度は「僕が手をあげたら逆になります」と声をかけ、手を挙げて①が鳴ったら青、②が鳴ったらオレンジに行くようにすると次々とエラーが起こっていく。さらにここで新たに③の音を聞かせ、「③の音が鳴ったら、直前の方向の逆に行ってください」と付け加えた。
実に4通りのパターンになったことでさらに複雑化していき、視覚、聴覚、知覚と思考、身体操作の5つの感覚・行動を同時に駆使しないと対応できなくなっていく。
だが、選手たちからは笑みが溢れ始め、混乱しながらも、そのカオスを楽しんでいるように見えた。この表情、雰囲気こそが脳が活性化し始めている兆候なのだろうとも受け止められた。

次は緑色と赤色のマーカーの前で対決するトレーニング。合図の音がなく鈴木氏が「赤色」と言ったら緑色を奪い合い、「緑色」と言ったら赤色を奪い合う。さらに音が1回鳴ったら赤色は赤色、緑色は緑色。音が2回鳴ったら音無しと同じ条件になり、音が3回鳴ったら1回鳴ったときと同じ条件になる。
さらにその場で足踏みをしながら、鈴木氏が「1」と言ったら両手は上、「2」は両手を左右に広げ、「3」は自分のお尻を両手でタッチし、「4」はその場でジャンプという動きを加えてから、音と色指定でマーカーを奪い合う対決をする。
「サッカーでよく『認知』と言うよね。情報を知覚、聴覚、視覚で取り入れて整理して、『精査→推論→判断』。この流れが大事だよ!」
マルチタスクを使う感覚を増やしてより複雑にしていく。

続いて行われたお手玉を使うトレーニング。
投げる選手と受け取る選手に分かれ、投げる選手が右手で投げたら、受け取る選手は右手でキャッチという条件をつけた後に、右手で投げたら受け手は右手でキャッチすると同時に左足を出すという条件が加わる。
次はボールが加わり、足の裏でパス交換をしながら、お手玉を最初の条件と同じで行い、次はインサイドでダイレクトパス、アウトサイドを使ったパス交換などが組み入れられていく。

記憶力が試されるトレーニングと目の焦点を瞬時に動かしてピントを当てるトレーニングを行い、内容の濃い1時間は終了。鈴木氏は最後に選手たちの前でこう口にした。
「脳がうまく使えずに、記憶の容量が少ないと、せっかくプレー中に3人目の動きとか周りの敵や味方の位置を見えたとしてもプレーするときには忘れてしまう。記憶が定着していないとプレーにいかせません。何かをしながら、何かをするという経験を増やすことで、脳の中のワーキングメモリが上がる。短い時間で覚えられる量を増やすことがサッカー面でも大きなプラスになります。例えばドリブルをするだけなら簡単かも知れませんが、ドリブルをしながらパスを考えたり、他のプレーを考えたりするようになった途端にプレーのパフォーマンスが下がる。それをなくすためのトレーニングだと思ってください」
鈴木氏のトレーニングは最後まで一貫していた。この感想から、なぜ鈴木氏は脳トレに興味を持ち、今日のように全国を回って指導をしているのかが気になった。
彼自身の話を伺うと、そこには自身の経験が大きく影響していたことが分かった。
プロサッカー選手を目指していた現役時代、難病に苦しみ、日本体育大時代には前十字靭帯断裂の大怪我を負い、1年間を棒に振った。
だが、この1年間で自身のリハビリのために何かできないかと探した先に出会ったのが、身体を動かさなくても成長できるトレーニングとして、前述したドイツの神経科学トレーニングだった。
鈴木氏が見つけたのはそのサッカー部門だった。興味が向いたら即行動の彼は、すぐに自身のリハビリに導入し、ただ自分がこなすだけではなく、神経科学トレーニングをより深く学び続けながら、リハビリの様子を動画に撮って、SNSを通じて発信するようになった。
その反響がどんどん広がっていき、いつしか彼はエキスパートとしての道を歩いていくのだった。
「僕たち人間が生きている中で遭遇する『ミス』のほとんどは脳による指令のエラーや脳のスペックが原因。僕のサッカー人生は脳のエラーが原因でやりたいことができなかった。自分のような人間を少しでも減らせないかと考えました」

ここで前提条件として伝えたいのは、彼が行っているのは『ブレインテック産業』の一環であるということ。
ブレインテックとはBrain(脳)とTechnology(技術)をかけ合わせた造語。脳神経科学とITを融合させて脳の状態を解析することによって、脳の動きの様々なメカニズムを解明していき、その解明したものをベースに様々なアプリケーションやサービスに活かしていく活動やビジネスがブレインテック産業と呼ばれる。
「ヨーロッパなどではブレインテック産業からプロスポーツ、学校教育、企業の社員教育、認知症予防事業など、様々な分野で神経科学の導入が進んでいる。その流れを日本で作りたいと思うようになりました」
その活動の一環を『第10回 Nike FC presented by SOCCER SHOP KAMO』で学ことができた。
「僕が大事にしているのは『TYN(=楽しく、予想外で、慣れない)運動』を通じて、脳を活性化させたり、目の焦点をしっかりとコントロールしたりすることで、これまでの『見る』がより『見える、記憶に残る』に変わっていくこと。情報を得る速度が上がり、定着するようになれば、あとはその情報をプレーに反映させるだけ。毎日コツコツと積み重ねることで成長を得られるので、選手たちには続けて欲しいですね」
継続は力なり。だが、ただ闇雲に続ければいい訳では無い。目的意識をはっきりと持ったトレーニングを継続することで、それが血肉となっていく。
続いて行われた吉永一明氏のトレーニングもまさにその要素が含まれていた。

PROFILE
鈴木 大地(Daichi Suzuki)

著者
安藤 隆人(Takahito Ando)