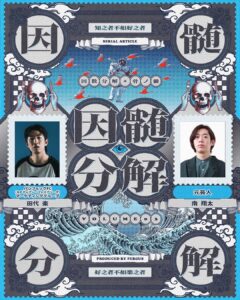Nike Football Academy at 修徳高校サッカー部 オフピッチ
日常の練習では学べない特別な体験を、特別な講師を呼んで提供する『NIKE FOOTBALL ACADEMY』。第11回目となる今回の舞台は、高円宮杯JFA U-18サッカーリーグT2(都2部)に所属する修徳高校サッカー部。春一番が吹き、真冬の寒さが少しだけ和らいだ2月中旬、東京都葛飾区の校舎にスポーツメディアFERGUSとして取材に赴いた。

オフピッチ講師・河内一馬の特異な経歴
学校の授業が終わった15時半頃、サッカー部Aチームの約30名が教室に入ってきた。まずは、フットボール以外の角度からフットボールを研究するオフピッチ(座学)の講義。今回の講師は河内一馬氏で、モニターを介しての講義となる。スピーカーから聞こえる河内氏の挨拶の言葉を皮切りに、オフピッチ開始。まずは河内氏の簡単な自己紹介から講義がスタートした。

東京都出身の河内氏は、FC東京の下部組織U-15むさしから実践学園高等学校サッカー部に進学。卒業後はサッカー専門学校JAPANサッカーカレッジに入学し、トレーニング理論や運動生理学などを学ぶ傍ら、夜間で鍼灸師専門学校に通い、鍼灸師国家資格を取得。在学中にはアルビレックス新潟ユースでインターンを経験した。卒業後、実践学園高等学校サッカー部コーチを2年間務めたのち、世界のサッカーを観るためにアジアやヨーロッパを中心に15ほどの国と地域を周った。帰国後、成蹊大学体育会サッカー部(東京都2部リーグ)のコーチを務めリーグ優勝・東京都1部昇格を果たし、翌年にはヘッドコーチを担当した。
2018年からアルゼンチンへ移住し、南米サッカー連盟における最上位カテゴリーの指導者ライセンスCONMEBOL PROを取得。帰国後の2021年シーズンから鎌倉インターナショナルFCの監督及びCBO(チーフブランディングオフィサー)に就任し、2022年にはチームを神奈川県1部昇格に導く。現在は監督を退任し、鎌倉インテルのTD(テクニカルディレクター)兼CBOを務めながら、株式会社 vennnのCEOとしてスポーツにおけるブランディングを主に、クリエイティブ制作やデザインなどの視覚領域に加え、コンセプトメイキング、言語化、執筆など言葉を用いた事業を展開している。
ーーーーー
その特異な経歴や現在の仕事内容から、サッカーが持つ文化としての豊かさや深さを多様な形で体現する、日本サッカー界要注目の人物であることが窺える。情報へのアクセスが容易になり、人生の選択肢が増え続けている現代においても、実際に河内氏のような存在を知り、その話を直接聞けることは、高校年代の選手たちにとって非常に有意義な体験になるのではないだろうか。
「サッカーやバスケだけ、日本は世界トップを争うことができていない」
河内氏による今回の講義のテーマ、「私たちはサッカーから何を学ぶべきか」がモニターに映し出される。講義の内容は、サッカー本大賞の大賞を受賞した彼の初著『競争闘争理論』をベースにしたものだという。
テーマの本丸に迫るべく、「サッカーとは何か?」という問いを最初の入口に設定した。それを考えていく上で、まずは東洋と西洋という二つの概念を意識するよう、生徒たちに語りかける。「日本人には東洋の思想が根付いていますが、現代社会のシステムには西洋由来のものがたくさんあります。サッカーも西洋で生まれたものです」と河内氏は説く。
そこから、スポーツ全般におけるサッカーの特異性へと話は進む。人間の体を研究するためにネズミを用いて実験、検証、比較という作業を行うように、サッカーを知るために他のスポーツとの共通点、類似点、相違点を紐解いていく。
河内氏の競争闘争理論において、スポーツは競争と闘争の2種類に大きく分類される。
・競争のスポーツ…陸上競技や水泳、体操など
→相手の空間に入れない競技や、競技の時間軸が異なっていても点数や評価で競うことができるスポーツ
・闘争のスポーツ…ボクシングやバスケットボール、サッカーなど
→同じ時間に同じ空間で行い、第三者の介入や妨害がルール上許容されているスポーツ
さらに、その分類は以下のようにより細かく定義される。
① 個人競争…短距離走、ゴルフなど
② 団体競争…リレー、シンクロナイズドスイミング、など
③ 個人闘争…ボクシング、剣道など
④ 団体闘争…サッカー、バスケなど
⑤ 間接的個人闘争…テニス、バドミントンなど
⑥ 間接的団体闘争…野球、バレーボールなど
上記のうち、「④の団体闘争(サッカーやバスケ)だけが、日本は世界トップを争うことができていない」と河内氏は話す。
確かにそうだ。オリンピックを例に挙げると、体操や柔道、スケートボードなどの個人競争と個人闘争では、これまでに多くのメダルを獲得している。4×100mリレーなどの団体競争でもメダルを争えるようになってきた。オリンピック以外で考えても、ボクシングには井上尚弥というモンスターがおり、間接的な団体競争である野球は、大谷翔平という稀代のスターを擁し、WBCでも世界王者に3度輝いている。
しかし、サッカーはW杯ベスト16の壁をいまだに越えられていない。チャンピオンズリーグやプレミアリーグでプレーする選手が次々と育ってきているように、日本サッカーのレベルが上がっていることは間違いない。ただし、2002年日韓W杯の初挑戦で超えられなかった壁が、20年以上経った今も同じように立ちはだかっているのもまた事実。河内氏は次のようにその理由を説明する。
「団体闘争(サッカーやバスケ)で日本がトップを争えていない理由は、日本人が持つ東洋的な文化、日本的な文化にあると考えています。その理由をこれから話していきますが、まずは出発点として、『サッカーが団体闘争のスポーツである』ということに気づいて欲しいです。その上でトレーニングや試合に臨んでもらえるだけでも、今日の講義の意味はあると思います」と河内氏は力を込めて伝える。

サッカー=団体闘争=“個人の成果”の足し算ではない
モニターに次の言葉が表示される。
・競争のスポーツ「正解を選択していく」
・闘争のスポーツ「選択を正解にしていく」
競争のスポーツである陸上競技や水泳は、試合に邪魔や妨害が入ることはルール上許されておらず、かつ、求められる正解が試合前にある程度判明している。例えば、オリンピックのマラソンに参加標準記録という明確なタイムが設けられているように。
一方、闘争に分類されるサッカーやボクシングなどは、邪魔や妨害が入るのが大前提であり、正解も事前には分かっていない。例えば、「サッカーは前方にあるゴールを目指すスポーツなので、前向きにプレーすることが正解」と思われがちだが、状況によってはバックパスをすることが正解になる場面も試合中に多々発生する。つまり、「こうすれば勝てる」という正解がないのだ。
では、正解がないスポーツにおいて、どのような行動が必要になるのだろうか。
「団体闘争のスポーツでは、自らの選択を正解にしていくことが必要になります。つまり、選択の“後”の行動が大事になる。そのためには“次に何をしなければいけないのか”を考え続けることが求められます。
これはサッカーだけでなくて、人生でも同じだと思います。あらかじめ正解が用意されている訳ではないですし、社会全体としても、より正解が用意されにくい社会へと変化していると感じています」
日本式の学校のテストや受験に代表されるように、「あらかじめ正解が用意されているものを日本人は得意としている」と河内氏は語る。だからこそ、日本人は競争のスポーツで結果を出しやすい。
言い換えれば、「サッカーは正解がないからこそ、日本人は苦手」ということ。それはなぜなのか。「正解の有無により、チームワークにおいて求められる行動や姿勢が全く異なる」という部分にその理由があるという。
・団体競争(リレーやシンクロ)
=正解が決まっている
=個人の成果の合計がチームの結果になる
→「チームワークにおいて衝突を必要としない」
・団体闘争(サッカーやバスケ)
=正解が決まっていない
=個人の成果の合計が結果に反映されるわけではない
→「チームワークにおいて衝突を必要とする」
なぜサッカーのチームワークでは衝突が必要なのか、河内氏は次のように説明する。
→個人のドリブルやパスが優れていても、チームとしての結果には繋がらない
→試合の結果そのものが、チームとしての結果
→チームとしての結果を求める上で、あらかじめ正解が示されているわけではない
→正解を目指す上で、それぞれの考えや意見が最初から一致することはほぼあり得ない
→だからこそ、衝突を繰り返し、考えや意見を擦り合わせていくことが必要になる
講義の冒頭に出てきた“東洋と西洋”という二つの概念が、ここで繋がる。「和をもって貴しとなす」という言葉に代表されるように、「日本人は、その場にいる全員が居心地良く過ごせる空間や雰囲気を作ることはすごく得意」と河内氏は指摘する。
一方で、「意見の異なる相手との話し合い(衝突)が苦手であり、サッカーにおいてはそれがマイナスに働いている」と河内氏は続ける。なぜならば、ここまで述べたように「サッカーは個人の成果の単純な足し算ではないから」である。
河内氏の話を聞いて、昨シーズンJ1連覇を成し遂げたヴィッセル神戸のことを思い浮かべた。連覇できた要因の一つとして、大迫勇也や武藤嘉紀、酒井高徳といった元海外組の選手たちが、練習から激しくプレーする習慣を持ち込んだから、というエピソードがメディアで頻繁に語られた。しかし、彼らがチームにもたらしたのはそれだけではないはずだ。
各々が理想とする戦術や試合運び、メンタリティ、それらを主張することを厭わず、むしろ衝突を繰り返していくことで、“言い合うことが当たり前”の文化が熟成した。その結果、日本のチームとしては珍しい、“プレー面でもメンタル面でも闘える集団”が完成したのではないだろうか。

サッカーで西洋的な価値観を学べるのはラッキー
講義を振り返りながら、なぜこのテーマを選んだのか、という視点から河内氏が生徒たちに語りかける。
「サッカーが団体闘争のスポーツであり、だからこそ何が必要とされるのかを理解した上でサッカーに向き合って欲しいと思い、このテーマを選びました。
サッカー以外においても、たとえば高校を卒業した後、自分とは異なる意見を持つ人や、異なる環境で育ってきた人と関わったり、一緒に仕事をする機会が増えていくと思います。大人になればなるほど、それは顕著になっていきます。
サッカーをやってきた君たちは、『チームワークに何を求められているのか?』という観点を持った上で、他者と関わり合っていくことができる。『意見の食い違いや衝突は、そもそも起きるのが当たり前だ』ということが頭に入っていれば、問題にもスムーズに対応できるはずです。日本の日常生活からはなかなか学び取りにくい西洋的な価値観を、サッカーから学べるのは、これからの人生においても非常にラッキーなことだと思います。
もしプロサッカー選手になれなかったり、プレーヤーとしてはサッカーを辞めてしまったとしても、サッカーを他分野に活かすことはできる、ということも伝えたいです。僕も高校生までは『サッカーしか知りません』という人でしたが、『どうすればサッカーを他に活かせるのか』ということをひたすら考えてきて、32歳になった今もずっと考え続けています。
皆さんにも考え続けて欲しいですし、今日の講義で紹介した競争闘争理論をぜひ参考にしてみて欲しいなと。興味が湧いた方はぜひ本を読んでみて、気になることがあれば何でも聞いてください。何でもお答えしますので。
講義は以上です。今日お伝えしたことを少しでも受け取っていただいて、高校サッカーを思う存分頑張って欲しいなと思います」
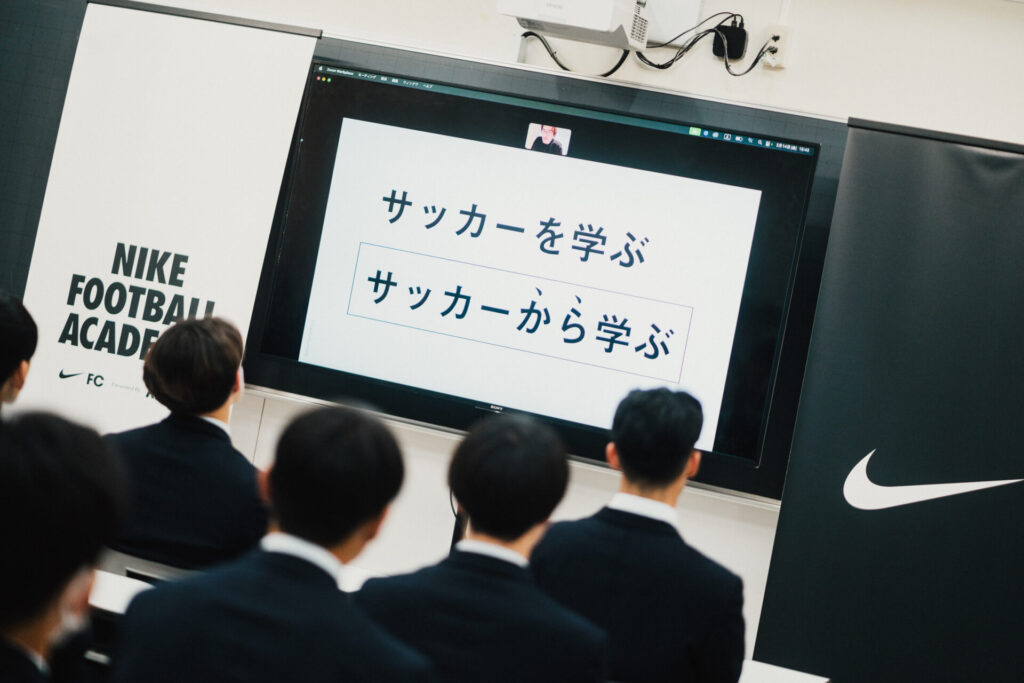
講義が終わった後の質疑応答にて、一人の生徒から次のような質問が飛んだ。
「団体闘争のスポーツであるサッカーでは、チームとしての戦い方が決まっている方が強いのでしょうか」
その質問に対し、河内氏は次のように答える。
「絶対的な正解を事前に知ることはできないものの、頻繁に起こるシーンは予想できますよね。その予想に基づき、チームとしての対応策を整理しておくことは、チームの助けになります。それがいわゆる戦術と呼べるものだと思います。
ただ、戦術を遂行するためだけにプレーすると、例外的な事象や不確定要素に対応できなくなる。よく言われる『日本人は臨機応変にプレーできない』というのが、まさにその部分だと思います。それらを頭に入れた上でプレーすることが大切だと感じます」
また、ある生徒はイベント終了後のインタビューで、講義の感想をこう答えてくれた。
「僕はチームにおける序列や自分の立ち位置を気にしてしまい、萎縮してしまう部分があるのですが…サッカーが団体闘争のスポーツということを今日の講義で学べたので、今後は序列を気にせずに、感じたことをもっと発言したり、自発的にプレーしていかないといけないな、と感じました」
新チームが発足して間もない現在、彼らはまだ1年生と2年生だ。プロを見据えている選手もいれば、高校卒業後の進路が明確には定まっていない選手も多くいるだろう。人生の岐路をこれから迎える選手たちにとって、今日の河内氏の言葉は大きな一つの指針となっていくに違いない。
PROFILE
河内 一馬(Kazuma Kawauchi)

PROFILE
佐藤 麻水(Asami Sato)